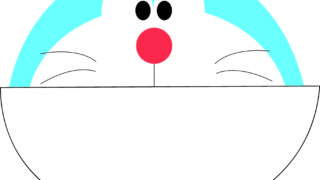「リングにかけろ」概要
作者/車田正美
掲載誌/週刊少年ジャンプ
連載期間/1972年2号~1981年44号
主な登場人物/高嶺竜児 高嶺菊 剣崎順 香取石松 志那虎一城 河井武士 など
主人公高嶺竜児がプロボクサーだった亡き父の遺志を継いで世界チャンピオンを目指すべく、姉である菊の教えを受けて成長していくいわゆるスポ根系のボクシング漫画。
略称「リンかけ」
リングにかけろ 名勝負 高嶺竜児vs剣崎順 2度目の対決PART②
竜児の消極的戦術
聖華学院での練習試合高嶺竜児vs剣崎順の2度目の対決。
試合は菊がタオルを投入したことで、一時中断したが、竜児は姉の忠告を退け、リングに戻ってくる。
そして試合再開。
けがのため、右の拳がまともに使えない竜児は左ジャブを打った後、剣崎から距離を取る、※ヒット&アウェイの戦法に出る。
これに業を煮やした剣崎、なぜ正々堂々と打ち合わないのかと竜児に問いただす。
(今のおれにはこの戦術しかない)
竜児はそう自分にいい聞かすが、かといってこのまま消極的なボクシングを続けていても勝ち目はあるのか?
「お前がこないなら、こっちからいってやる」
煮え切らない竜児にいらつく剣崎はパンチの集中砲火を容赦なく浴びせる。
竜児、今度はロープを背にがっちりと亀のようにガードを固めてこれを耐え忍ぶ。
ローブ・ア・ドープだ。
「やられっぱなしに見えるが、見た目ほどにはダメージはない。剣崎のパンチの威力はロープで分散されている」
試合を見に来ていた志那虎一城の解説が入る。
「見損なったぜ!」
怒り心頭に達した剣崎は猛然とダッシュし、防戦一方の竜児に必殺のアッパーカットを食らわす。
竜児たまらず、ダウンするが何とか立ち上がり、その後1R終了のゴングに救われる。
ヒット&アウェイ戦法
フットワークを駆使して、接近して打ってすぐ離れる、という一連の動作を基本とするもの。ボクシングにおける戦術の一つ。
ローブ・ア・ドープ
ロープの弾力を利用して相手のパンチの衝撃を吸収するテクニック。
1974年に行われた当時の世界ヘビー級チャンピオン、ジョージ・フォアマンとモハメド・アリの一戦でアリがこの戦術を使い、逆転勝利を奪う。
ザイールの首都キンシャサで行なわれたことから、この試合は「キンシャサの奇跡」と呼ばれている。
左を制する者は世界を制す。
ROUND2
2ラウンドが始まっても竜児の消極的戦術は基本変わらない。
いまだ突破口が見いだせない、けっこうグダグダな展開だ。
剣崎は相変わらずおかまいなしに、バシバシパンチを打ってくる。
猛攻撃を行うことで、竜児の闘志に火をつけるねらいだ。
ここで追い込まれた竜児は無意識に禁断の右ストレートらしきパンチを放つ。
これには剣崎も意表をつかれダウンするが、確実さを欠いた中途半端なパンチであったため、ダメージは最小限の模様。
打った竜児も「なぜあんな打ち方をしてしまったのか…」
と自問自答する。
おそらくこの場にはいないけれども、竜児の右拳を心配した菊の執念が作用したパンチだったのではないかと分析する。
何と美しく、固い兄弟の絆であることか。
そして竜児はもう一度右ストレートを放とうとするが、剣崎が飛び込んできたところへ一瞬のフェイントで左ストレートをたたき込む。(これも菊の遠隔操作?)
このパンチはフェイントというよりは、これ以上右を使えば、今度こそ選手生命に響くと咄嗟に体が判断し、本能的に左を放ったのでは?と推測される。
てっきり右でくるかとおもいきや竜児が左ストレートを打ってきたことで剣崎はぴんと来た。
どうやら竜児は右手を相当痛めている。
さすが、天才の直感である。
「この試合やめだ! 怪我人とやったって意味がねえ!」
竜児が試合続行不可能と判断した剣崎はそういい放つ。
しかし、この剣崎の発言に異を唱えるものがいた。
月島五中のボクシング顧問、美人の朝丘先生が突如、吉田松陰の話を引き合いに出して、
「人間の本義は約束を守ることである」
と剣崎を諭す。
この話にほだされた剣崎は取り巻きの部員にグローブを外させ、わざと自らの右拳をコーナーの鉄柱にしこたまぶつける。
拳は割れ、鮮血がほとばしる。
「これで五分と五分だ」
「左を制するものは世界を制す」
剣崎の口からボクシング界に脈々と語り継がれる言葉が発せられる。
2人はこの言葉通り、左と左、男と男の壮絶な相討ちを行う。
この試合最大の見せ場だ。
いつのまにか菊もリングサイドに戻り、2人の死闘を静かに見守っている。
結果はダブルノックダウン。
勝敗は判定にゆだねられ58対50で剣崎の勝利。
しかしそんな判定などもはやどうでもいいほど、2人は魂と魂を本気でぶつけあったのだ。
この試合を期に竜児と剣崎はお互いを認め合い、切磋琢磨していくことになる。
- 高嶺竜児 必殺技 ブーメランフック
- 高嶺竜児 必殺技 ブーメランスクエアー・ブーメランテリオス
- 高嶺竜児 必殺技 ウイニング・ザ・レインボー
- 高嶺菊 竜児を世界チャンピオンに育てた名トレーナー
- 名勝負を振り返る 高嶺竜児vs辻本昇PART①
- 名勝負を振り返る 高嶺竜児vs辻本昇PART②
- 名勝負を振り返る 都大会決勝 高嶺竜児vs剣崎順PART①
- 名勝負を振り返る 都大会決勝 高嶺竜児vs剣崎順PART②
- 名勝負を振り返る 高嶺竜児vs剣崎順 2度目の対決PART①
- 名勝負を振り返る 高嶺竜児vs剣崎順 2度目の対決PART②
- 剣崎順 必殺技解説とその人物像に迫る その①
- 剣崎順 必殺技解説とその人物像に迫る その②
- 香取石松 必殺技解説とその人物像に迫る
- 志那虎一城 必殺技解説とその人物像に迫る その①
- 志那虎一城 必殺技解説とその人物像に迫る その②
- 河井武士 必殺技解説とその人物像に迫る
- 影道総帥 (影道殉) の必殺技と特殊能力を分析
- チャンピオンカーニバルをダイジェストで振り返るPART①
- チャンピオンカーニバル決勝 高嶺竜児vs河井武士PART①
- チャンピオンカーニバル決勝 高嶺竜児vs河井武士PART②
- 日米決戦を斬る 日本代表vsアメリカ選抜
- 名勝負を振り返る 日米決戦 高嶺竜児vsブラックシャフト
- 高嶺竜児 影道の塔での戦いPART①
- 高嶺竜児 影道の塔での戦いPART②
- 日本代表vs影道 千里丘陵血戦を斬るPART①
- 日本代表vs影道 千里丘陵血戦を斬るPART②
- 名勝負を振り返る 千里丘陵決戦 高嶺竜児vs影道総帥
- 高嶺竜児に関係する登場人物紹介
- 世界大会準々決勝 日本代表vsフランス代表